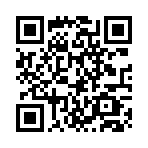4. 薫風天狐
薫風天狐(くんぷうてんこ)
作曲者;山口雄介、石森裕章(2013年作曲 2016年リニューアル*)
ここは駿河国足久保。足久保はお茶処*、春風にお茶の薫りが運ばれて、野狐たちが遊び出す。
そんな緑豊かな足久保に静かに佇む狐石伝説をイメージして作曲されました。
するが路や はなたちばなも 茶のにおい (松尾芭蕉)
この句が刻まれた日本一大きな句碑「狐石」が足久保にはあります。その昔、この石の下に狐が住んでいたため村人から「狐石」と呼ばれるようになったとか。昔から狐は歳を重ねるにつれ、その呼び名が変わる生き物と言われています。
野狐(やこ) …無邪気に遊びまわる子供の時代。
↓
気狐(きこ) …やがて大人になって人間を騙すようになる。
↓
天狐(てんこ) …千年を生き、神の域に達したもの。世の中に吉兆をもたらす。
この曲は、狐石の狐が野狐から気狐、そして天狐へと成長して行く様子、また天狐となった狐がお茶の薫りに魅せらせて、新茶の季節に足久保の空を楽しげに飛び回っている様子を表現しています。2匹の野狐のチャッパのかけあいから始まり、オープニングは気狐に生まれ変わる混沌とした様子を表現しました。中盤の笛と大太鼓のソロは、菩薩が降りて来て天狐になる様子をイメージしました。約6分に渡る、華やかな大曲です。
*リニューアル前はオープニングの笛と締め太鼓が印象的でした。笛のロングトーンはシンプルなメロディーながら腹式呼吸がしっかりしていないとできないもの。締め太鼓はテンポを速くしたり遅くしたりすることで、空間の歪みを感じる独特なものでした。リニューアル前と後、どちらもイイ!
*鎌倉時代、円爾弁円(聖一国師・しょういちこくし)が仏教修行のため渡った宋から茶樹の種を持ち帰り、現在の静岡市葵区足久保に植えたことが、静岡茶の始まりと伝えられています。足久保は静岡茶発祥の地だったんですね。
(文 団長、キョン、綾)
作曲者;山口雄介、石森裕章(2013年作曲 2016年リニューアル*)
ここは駿河国足久保。足久保はお茶処*、春風にお茶の薫りが運ばれて、野狐たちが遊び出す。
そんな緑豊かな足久保に静かに佇む狐石伝説をイメージして作曲されました。
するが路や はなたちばなも 茶のにおい (松尾芭蕉)
この句が刻まれた日本一大きな句碑「狐石」が足久保にはあります。その昔、この石の下に狐が住んでいたため村人から「狐石」と呼ばれるようになったとか。昔から狐は歳を重ねるにつれ、その呼び名が変わる生き物と言われています。
野狐(やこ) …無邪気に遊びまわる子供の時代。
↓
気狐(きこ) …やがて大人になって人間を騙すようになる。
↓
天狐(てんこ) …千年を生き、神の域に達したもの。世の中に吉兆をもたらす。
この曲は、狐石の狐が野狐から気狐、そして天狐へと成長して行く様子、また天狐となった狐がお茶の薫りに魅せらせて、新茶の季節に足久保の空を楽しげに飛び回っている様子を表現しています。2匹の野狐のチャッパのかけあいから始まり、オープニングは気狐に生まれ変わる混沌とした様子を表現しました。中盤の笛と大太鼓のソロは、菩薩が降りて来て天狐になる様子をイメージしました。約6分に渡る、華やかな大曲です。
*リニューアル前はオープニングの笛と締め太鼓が印象的でした。笛のロングトーンはシンプルなメロディーながら腹式呼吸がしっかりしていないとできないもの。締め太鼓はテンポを速くしたり遅くしたりすることで、空間の歪みを感じる独特なものでした。リニューアル前と後、どちらもイイ!
*鎌倉時代、円爾弁円(聖一国師・しょういちこくし)が仏教修行のため渡った宋から茶樹の種を持ち帰り、現在の静岡市葵区足久保に植えたことが、静岡茶の始まりと伝えられています。足久保は静岡茶発祥の地だったんですね。
(文 団長、キョン、綾)
2020年07月29日 Posted by 足久保太鼓 at 21:58 │Comments(0) │曲の由来
3. ひまち日和
ひまち日和
作曲者:佐藤元、山口雄介(2012年)
皆さんおひまちって知っていますか?聞き慣れない言葉かもしれませんが、ひまちとは日を待つ、つまりお祭りのことです。
足久保でも50年ほど前までは、村の若者が朝から丸太で舞台を作り、夜には村人たちによる演芸が行われていました。
また絵や文字を描いた手作りの灯篭を沿道に並べ、夜道を照らしていました。何とも風情がありますね。
普段は農作業が忙しく話す機会の少ない若い男女にとって、おひまちは待ち遠しいイベントであったに違いありません。
おひまちの夜に新しい恋が芽生えたことも想像に難くないでしょう。
このおひまちを題材として、私たちの両親や祖父母の時代を思い浮かべながら創作した曲が「ひまち日和」です。
この曲はおひまちを楽しむ村人たち、若い男女の恋の駆け引きを桶胴太鼓で表現しています。
桶胴太鼓は軽く、機動力があるのが特徴です。担いだり踊ったりしながら演奏することができ、派手なパフォーマンスが魅力です。
でも…今はおひまちは、なくなったんでしょう?
いえいえ、実は数年前におひまちが復活したんです!現在は毎年10月中旬*に「おひまち灯ろう」祭りがここ足久保で行われています。
どこか懐かしい、個性あふれるあたたかいあかりを楽しみに、地元はもとより遠方からもたくさんの人が訪れてくださいます。
皆さんも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。お祭りの賑わいの中、甘酸っぱい恋のワンシーンが見られるかもしれませんよ。
*詳しい日程はブログ、Facebookをチェック!
(文 団長、綾)
作曲者:佐藤元、山口雄介(2012年)
皆さんおひまちって知っていますか?聞き慣れない言葉かもしれませんが、ひまちとは日を待つ、つまりお祭りのことです。
足久保でも50年ほど前までは、村の若者が朝から丸太で舞台を作り、夜には村人たちによる演芸が行われていました。
また絵や文字を描いた手作りの灯篭を沿道に並べ、夜道を照らしていました。何とも風情がありますね。
普段は農作業が忙しく話す機会の少ない若い男女にとって、おひまちは待ち遠しいイベントであったに違いありません。
おひまちの夜に新しい恋が芽生えたことも想像に難くないでしょう。
このおひまちを題材として、私たちの両親や祖父母の時代を思い浮かべながら創作した曲が「ひまち日和」です。
この曲はおひまちを楽しむ村人たち、若い男女の恋の駆け引きを桶胴太鼓で表現しています。
桶胴太鼓は軽く、機動力があるのが特徴です。担いだり踊ったりしながら演奏することができ、派手なパフォーマンスが魅力です。
でも…今はおひまちは、なくなったんでしょう?
いえいえ、実は数年前におひまちが復活したんです!現在は毎年10月中旬*に「おひまち灯ろう」祭りがここ足久保で行われています。
どこか懐かしい、個性あふれるあたたかいあかりを楽しみに、地元はもとより遠方からもたくさんの人が訪れてくださいます。
皆さんも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。お祭りの賑わいの中、甘酸っぱい恋のワンシーンが見られるかもしれませんよ。
*詳しい日程はブログ、Facebookをチェック!
(文 団長、綾)
2020年04月29日 Posted by 足久保太鼓 at 19:22 │Comments(0) │曲の由来
2. 駿墨
駿墨(するすみ)
作曲者: 加藤貴彦 (2011年作曲 2018年リニューアル)
静岡市藁科地区に実在したとされる漆黒の名馬・駿墨(するすみ)をテーマとした、足久保太鼓を代表する名曲です。
当時のメンバーによる完全オリジナル曲で、2018年にリニューアルしています。
足久保から釜石峠を越えると、静岡茶の祖「聖一国師(しょういちこくし)」が生まれた集落があります。
駿墨はここで育てられ、かの源頼朝に献上されました(平家物語等 諸説あり)。
のちに*梶原景季(かじわらのかげすえ)に下され、1184年宇治川の戦いで佐々木高綱が有する白馬の名馬「*いけづき(生食)」と先陣を争ったといわれます。
敵陣の中を縦横無尽に走り回り、たくましく戦国の世を生き抜いた駿墨や当時の武将の生き様が力強い太鼓のリズムとともに溢れてきます。
前列に一列ずらっと並んだ長胴太鼓はさしずめ前進する武将達か、後ろに控える組太鼓と大太鼓はそれを鼓舞する援軍か…
思わず息を呑み、知らず知らず引き込まれてしまう。特に男性に人気のある曲です。
足久保太鼓のエンディングに必ず演奏される、毎回大きな拍手をいただく曲です。
*梶原景季ははじめ生食が欲しかったのですが、佐々木高綱に下げられてしまったので、代わりに駿墨がどうしても欲しくて頼朝におねだりしたそうです。手に入った時はさぞ嬉しかったことでしょう。
*いけづき(生食)は人でも動物でも何でもかじりつく血気盛んな、やはりたくましい馬だったそうです。
(文 団長、キョン、綾)
作曲者: 加藤貴彦 (2011年作曲 2018年リニューアル)
静岡市藁科地区に実在したとされる漆黒の名馬・駿墨(するすみ)をテーマとした、足久保太鼓を代表する名曲です。
当時のメンバーによる完全オリジナル曲で、2018年にリニューアルしています。
足久保から釜石峠を越えると、静岡茶の祖「聖一国師(しょういちこくし)」が生まれた集落があります。
駿墨はここで育てられ、かの源頼朝に献上されました(平家物語等 諸説あり)。
のちに*梶原景季(かじわらのかげすえ)に下され、1184年宇治川の戦いで佐々木高綱が有する白馬の名馬「*いけづき(生食)」と先陣を争ったといわれます。
敵陣の中を縦横無尽に走り回り、たくましく戦国の世を生き抜いた駿墨や当時の武将の生き様が力強い太鼓のリズムとともに溢れてきます。
前列に一列ずらっと並んだ長胴太鼓はさしずめ前進する武将達か、後ろに控える組太鼓と大太鼓はそれを鼓舞する援軍か…
思わず息を呑み、知らず知らず引き込まれてしまう。特に男性に人気のある曲です。
足久保太鼓のエンディングに必ず演奏される、毎回大きな拍手をいただく曲です。
*梶原景季ははじめ生食が欲しかったのですが、佐々木高綱に下げられてしまったので、代わりに駿墨がどうしても欲しくて頼朝におねだりしたそうです。手に入った時はさぞ嬉しかったことでしょう。
*いけづき(生食)は人でも動物でも何でもかじりつく血気盛んな、やはりたくましい馬だったそうです。
(文 団長、キョン、綾)
2020年04月04日 Posted by 足久保太鼓 at 21:23 │Comments(0) │曲の由来
1. 大蛇
大蛇(オロチ)
作曲者:松永勇次(2009年)
正式名称は牛が峰大蛇太鼓。足久保、水見地区に古くから伝わる大蛇伝説をもとに作曲されました。
プロの作曲家である松永勇次さんに依頼し作っていただいた、足久保太鼓の記念すべき第1曲目です。
太鼓の楽譜はリズム譜なので、打ち方や振り付けは団員で試行錯誤して作り上げました。改良を重ね現在に至ります。
篠笛のソロと大太鼓からなる導入部は物語を予感させ、直後の長胴太鼓の曲線的な打ち方は蛇の鎌首を表現しています。
全体的にメロディアスで、場面場面のストーリーが映像となって現れるようです。
[高山の沼の主]
昔、足久保の隣村に住んでいる長者の娘のもとへ、毎晩のように通ってくる美しい若者がいた。
素性を語らない若者を不審に思った娘の母親は、若者の着物に糸を縫い付けるよう娘に伝える。
翌朝、長者の下男がその糸を辿ったところ、それは高山(牛ケ峰)の池の中に続いていた。若者はこの池の主「大蛇」の化身であった。
それを知った長者は怒り狂い、人夫を引き連れて高山に登り、大きな石を焼き大蛇の住む池に次々と投げ込んだ。すると、たちまち煮えたぎった池の熱さに耐えきれなくなった大蛇はその姿を表す。あまりの恐ろしさに腰を抜かす下男達であったが、生かしておいてはのちのち祟りになる、とさらに焼き石を投げ込み、大蛇は片目を潰されてしまう。沼から追い出された大蛇は、足久保の麓の諸川池(舟渡池)にくだり、安倍川を渡り鯨ケ池まで逃げる…。*
静岡県の民話(日本児童文学協会・偕成社)より抜粋
*ちなみに鯨ケ池では、近年まで片目の魚が多く目撃されたとのこと。現在はどうなのでしょうか(釣りキチ三平にも載っています)。
(文 団長、綾)
作曲者:松永勇次(2009年)
正式名称は牛が峰大蛇太鼓。足久保、水見地区に古くから伝わる大蛇伝説をもとに作曲されました。
プロの作曲家である松永勇次さんに依頼し作っていただいた、足久保太鼓の記念すべき第1曲目です。
太鼓の楽譜はリズム譜なので、打ち方や振り付けは団員で試行錯誤して作り上げました。改良を重ね現在に至ります。
篠笛のソロと大太鼓からなる導入部は物語を予感させ、直後の長胴太鼓の曲線的な打ち方は蛇の鎌首を表現しています。
全体的にメロディアスで、場面場面のストーリーが映像となって現れるようです。
[高山の沼の主]
昔、足久保の隣村に住んでいる長者の娘のもとへ、毎晩のように通ってくる美しい若者がいた。
素性を語らない若者を不審に思った娘の母親は、若者の着物に糸を縫い付けるよう娘に伝える。
翌朝、長者の下男がその糸を辿ったところ、それは高山(牛ケ峰)の池の中に続いていた。若者はこの池の主「大蛇」の化身であった。
それを知った長者は怒り狂い、人夫を引き連れて高山に登り、大きな石を焼き大蛇の住む池に次々と投げ込んだ。すると、たちまち煮えたぎった池の熱さに耐えきれなくなった大蛇はその姿を表す。あまりの恐ろしさに腰を抜かす下男達であったが、生かしておいてはのちのち祟りになる、とさらに焼き石を投げ込み、大蛇は片目を潰されてしまう。沼から追い出された大蛇は、足久保の麓の諸川池(舟渡池)にくだり、安倍川を渡り鯨ケ池まで逃げる…。*
静岡県の民話(日本児童文学協会・偕成社)より抜粋
*ちなみに鯨ケ池では、近年まで片目の魚が多く目撃されたとのこと。現在はどうなのでしょうか(釣りキチ三平にも載っています)。
(文 団長、綾)