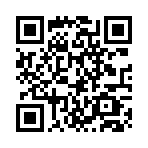法明寺 本開帳
この本開帳では、行基が彫ったという観世音菩薩のお姿が拝見できます。
足久保太鼓も、昨日17日のオープニングと、本日18日の2回演奏させていただきました。
この観世音菩薩に関する言い伝えはこのようなものです
今から1200年ほど前、奈良の都では聖武天皇がご病気で容態が悪かったので、陰陽博士に占わせたところ、「東の国に、千年を経た楠の大木があり、樹の寿命が尽きようとしているので、尊い僧に仏体を彫刻させて拝んだならば、天皇の病気も治るであろう」ということなので、徳の優れた有名な行基という僧侶を駿河国へ下らせた。
そのころ、法明寺の境内に、長さ三十三尋(約50メートル)直径十三間(約24メートル)もの楠の大木があったが、夜になると怪しい光を出していた。
この大木のことに違いない、ということで切り倒してみると、切り口からは真っ赤な血がコンコンと湧き溢れ、足久保川は樹液で真っ赤に染まったという。
行基は身を清め、一刀三礼といって、刃を当てるたびごとに三回拝んで、七体の観世音菩薩を彫り終えた。
これを駿河国府に近い七つのお寺に安置して、十七日の間天皇の後脳平癒の祈願を執り行い、天皇の病気も治ったという。
行基は楠の切り株の近くにお堂を建て、その中に観世音菩薩を安置した。
これが後に足久保の高福山法明寺となった。
行基の彫刻した七体の仏像を納めた寺は、慈悲尾山増善寺・瑞祥山建穂寺・普陀落山久能寺・鷲峰山霊山寺・大窪山徳願寺布袋山平沢寺とこの法明寺である。
皆さんも足久保にお越しの際は是非この法明寺へも足をお運びください。
次回は6年後に半開帳が行われます。