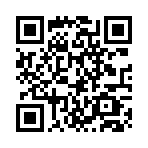2. 駿墨
駿墨(するすみ)
作曲者: 加藤貴彦 (2011年作曲 2018年リニューアル)
静岡市藁科地区に実在したとされる漆黒の名馬・駿墨(するすみ)をテーマとした、足久保太鼓を代表する名曲です。
当時のメンバーによる完全オリジナル曲で、2018年にリニューアルしています。
足久保から釜石峠を越えると、静岡茶の祖「聖一国師(しょういちこくし)」が生まれた集落があります。
駿墨はここで育てられ、かの源頼朝に献上されました(平家物語等 諸説あり)。
のちに*梶原景季(かじわらのかげすえ)に下され、1184年宇治川の戦いで佐々木高綱が有する白馬の名馬「*いけづき(生食)」と先陣を争ったといわれます。
敵陣の中を縦横無尽に走り回り、たくましく戦国の世を生き抜いた駿墨や当時の武将の生き様が力強い太鼓のリズムとともに溢れてきます。
前列に一列ずらっと並んだ長胴太鼓はさしずめ前進する武将達か、後ろに控える組太鼓と大太鼓はそれを鼓舞する援軍か…
思わず息を呑み、知らず知らず引き込まれてしまう。特に男性に人気のある曲です。
足久保太鼓のエンディングに必ず演奏される、毎回大きな拍手をいただく曲です。
*梶原景季ははじめ生食が欲しかったのですが、佐々木高綱に下げられてしまったので、代わりに駿墨がどうしても欲しくて頼朝におねだりしたそうです。手に入った時はさぞ嬉しかったことでしょう。
*いけづき(生食)は人でも動物でも何でもかじりつく血気盛んな、やはりたくましい馬だったそうです。
(文 団長、キョン、綾)
作曲者: 加藤貴彦 (2011年作曲 2018年リニューアル)
静岡市藁科地区に実在したとされる漆黒の名馬・駿墨(するすみ)をテーマとした、足久保太鼓を代表する名曲です。
当時のメンバーによる完全オリジナル曲で、2018年にリニューアルしています。
足久保から釜石峠を越えると、静岡茶の祖「聖一国師(しょういちこくし)」が生まれた集落があります。
駿墨はここで育てられ、かの源頼朝に献上されました(平家物語等 諸説あり)。
のちに*梶原景季(かじわらのかげすえ)に下され、1184年宇治川の戦いで佐々木高綱が有する白馬の名馬「*いけづき(生食)」と先陣を争ったといわれます。
敵陣の中を縦横無尽に走り回り、たくましく戦国の世を生き抜いた駿墨や当時の武将の生き様が力強い太鼓のリズムとともに溢れてきます。
前列に一列ずらっと並んだ長胴太鼓はさしずめ前進する武将達か、後ろに控える組太鼓と大太鼓はそれを鼓舞する援軍か…
思わず息を呑み、知らず知らず引き込まれてしまう。特に男性に人気のある曲です。
足久保太鼓のエンディングに必ず演奏される、毎回大きな拍手をいただく曲です。
*梶原景季ははじめ生食が欲しかったのですが、佐々木高綱に下げられてしまったので、代わりに駿墨がどうしても欲しくて頼朝におねだりしたそうです。手に入った時はさぞ嬉しかったことでしょう。
*いけづき(生食)は人でも動物でも何でもかじりつく血気盛んな、やはりたくましい馬だったそうです。
(文 団長、キョン、綾)
2020年04月04日 Posted by 足久保太鼓 at 21:23 │Comments(0) │曲の由来
曲紹介2
菜の花が落ち着いて、桜の季節ですね。
ここ足久保も、川沿いの桜並木が満開です。
足久保は大きな桜の木が多く、夜稽古に行く途中の夜桜がとても幻想的です。
世の中はコロナウイルスが猛威を奮っていますが、季節は変わらず流れていくようです。
ちなみに日本の山桜は100種類以上あるそうですよ。
さて今回は曲紹介の第2弾!足久保といえばこの曲。なんとこの曲を演奏したくて入団したメンバーもいます。
ぜひ曲の由来をご覧ください。
ここ足久保も、川沿いの桜並木が満開です。
足久保は大きな桜の木が多く、夜稽古に行く途中の夜桜がとても幻想的です。
世の中はコロナウイルスが猛威を奮っていますが、季節は変わらず流れていくようです。
ちなみに日本の山桜は100種類以上あるそうですよ。
さて今回は曲紹介の第2弾!足久保といえばこの曲。なんとこの曲を演奏したくて入団したメンバーもいます。
ぜひ曲の由来をご覧ください。